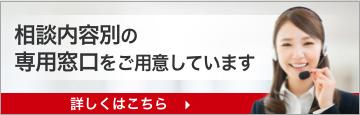著作権譲渡契約の際に知っておくべきポイントを岡山の弁護士が解説
- 商標・特許・知的財産
- 著作権
- 譲渡
- 岡山
- 弁護士

著作権とは、創作した作品の利用許諾や利用禁止を求められる権利です。日本の法制度では、著作権を侵害してはいけないことが規定されていますが、今日に至るまでそれをめぐる問題は多く発生しています。
岡山県でも、パンフレット作成時にイラストを利用したことが著作権侵害にあたるとして、イラストレーターやストックフォト会社から訴えられるという事例がありました。
もし著作者以外の事業者が著作物を自由に利用したい場合、後にトラブルが起きないように、著作権譲渡契約を交わして著作権を譲渡してもらうことが検討されます。本記事で、著作権とは何かを踏まえた上で、契約を交わす際の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が解説します。
1、著作権とは
著作権とは、著作物を財産として所有したり、それの利用を許諾したり禁止したりできる知的財産権のひとつです。著作物は、著作権法によれば思想または感情を創作的に表現したものであり、文章や写真、映像、音楽、コンピュータプログラムなどがそれに当てはまります。
-
(1)著作権と著作者
著作権が具体的に保護しているのは、著作権法第21条から第28条までに記載されている権利です。すなわち、著作物を印刷などによって複製する権利(複製権)、著作物を公に上演したり演奏したりする権利(上演権・演奏権)、著作物を口頭で公に伝える権利(口述権)などです。著作権を侵害した場合、10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
一方、著作物を創作した者を著作者といいます。法律では、著作者には、上述した著作権とは別に、人格的利益を保護する権利があると定められています(著作者人格権)。
たとえば、著作者には公表権というものがあり、まだ公表していない著作物を自分で公表するかどうか決めることが可能です。これ以外にも、著作物に著作者名をつけるかどうかなどを決められる権利(氏名表示権)や、勝手に著作物が改変されない権利(同一性保持権)を有しています。 -
(2)著作権の譲渡について
著作権は、著作権法第61条に基づき、全部またはその一部を譲渡することが可能です。著作権が譲渡された場合、著作権を譲受側が有することになります。このとき、後になってトラブルが起きないように、譲渡側と譲受側が交わすのが著作権譲渡契約書です。
著作権の譲渡契約は、たとえばソフトウェアの委託会社とそれの開発会社、ライターとメディア運営会社、作曲家や作詞家と音楽出版社(音楽出版者)などでよく交わされます。ちなみに、映画の場合は、著作者はプロデューサーや監督など全体的に創作に寄与した者となりますが、著作権は映画製作者に帰属することになります。
一方、著作者人格権は、契約によって譲渡してもらうことはできません(著作権法第59条)。したがって著作権譲渡契約の内容と譲受側の行為によっては、譲渡契約を締結したにもかかわらず、著作権法違反に問われる可能性があります。 -
(3)広義の著作権
著作権法では、著作権や著作者人格権以外にも、歌手や俳優などの実演家、レコード製作者、放送事業者などに与えられる権利(著作隣接権)についても定められています。たとえば、実演家が自分の実演を録音・録画する権利(録音権・録画権)や、レコード製作者がレコードを複製する権利(複製権)などです。
なお、著作権、著作者人格権、著作隣接権の3つをあわせて広義の著作権と呼ぶこともあります。ただし、この記事では著作権=財産権としての著作権とし、著作者人格権や著作隣接権は別ものとして解説します。
2、著作権を譲渡する場合は「著作権譲渡契約書」を交わす
前章で紹介したように、著作者から著作権を譲渡してもらいたい場合は、著作権譲渡契約書を交わすのが通例です。
では、契約書を締結する場合、どのような点に気をつければいいのでしょうか。著作権すべてを譲渡してもらう場合と一部を譲渡してもらう場合、それぞれに分けてご紹介しましょう。
-
(1)著作権すべてを譲渡してもらう場合の注意点
もっとも注意しなければいけないのが、著作権法第27条で規定されている翻訳権・翻案権等と、同第28条で規定されている二次的著作物の利用に関する権利の扱いです。著作権法第61条第2項では、譲渡契約においてこれらの権利に関して特に記載がない場合は、著作者に留保されると規定されています。
したがって、もし著作権全部を譲渡してもらいたいときは、契約書に「著作権全部(著作権法第27条および第28条で規定されている権利を含む)」と記載しなければいけません。
そのため、もし「著作権全部を譲渡する」とだけ決められた契約だと、著作権法第28条に抵触して著作者から著作権法違反だと主張される可能性があります。
また、著作者人格権についても気をつけなければいけません。全部を譲渡する契約をした場合でも、著作者人格権は著作者に留保されます。そのため、契約書では「著作者は、本著作物に関する著作者人格権を行使しないものとする」「甲は、本著作物の著作者人格権を、乙や乙が指定する第三者に対して行使しない」などと記載するのが一般的です(これを著作者人格権不行使特約といいます)。
もしこの記載が漏れてしまうと、ソフトウェアの開発会社がそのソフトウェアを勝手に公表する、委託会社に改変をしてほしくないと指摘する、といった可能性があります。 -
(2)著作権の一部を譲渡してもらう場合の注意点
著作権譲渡契約の中には、著作権の一部を譲渡してもらうパターンがあります。たとえば、映画の上映権だけを譲渡する、美術の展示権だけを譲渡するなどです。譲渡の期間を限定したり、指定した地域のみならOKとしたりする譲渡も、このパターンに含まれます。
著作権の一部を譲渡してもらう場合、注意しなければいけないのは、どこまでがOKでどこからがNGなのか明確にすることです。この点が曖昧なために、著作者側から思わぬ形で訴えられてしまうケースは少なくありません。
3、著作権の『譲渡』と『利用許諾』の違い
著作権の譲渡を考えるとき、利用許諾との違いを理解するのも大切です。ここでは、ソフトウェアの開発を委託した会社と開発した会社の関係を例にとりながら、譲渡にはできて利用許諾にはできないことをご紹介します。
-
(1)譲渡なら著作物を独占できる
ソフトウェアの開発会社から著作権が譲渡されれば、委託会社がその著作物の利用を許諾したり禁止したりできます。そのため、「せっかくお金を支払って開発してもらったのに、別の事業者も同じソフトウェアを利用している」といった事態を未然に防げます。また万が一、そうした事態に陥ったときでも、委託会社が相手事業者を訴えることが可能です。
一方、利用許諾の場合は、著作者が利用を許可しているだけに過ぎず、著作権は著作者のもとにあります。そのため、たとえば開発会社が、別の事業者に開発されたソフトウェアの利用許諾をしても委託会社は一切関与できません。また、まったく関係のない事業者が悪用した場合、著作者である開発会社は訴えることができますが、委託会社は裁判を起こせないことになります。 -
(2)譲渡なら第三者に著作権譲渡が可能
著作権が譲渡された場合、委託会社はそれを別の事業者に譲渡したり、ソフトウェアの利用許諾を出したりできます。もちろん、一部の権利だけ譲渡する、利用期間を限定するなども可能です。
一方、利用許諾の場合は、委託会社は当然ながら著作権を譲渡できません。また、特段の合意がない限り、利用許諾についても同様です。
また、利用許諾では開発会社が引き続き著作権を持っているので、開発会社は委託会社以外の会社に譲渡できます。
4、著作権譲渡契約書のひな形をそのまま利用するのは注意が必要
著作権の譲渡と利用許諾の項目で見てきたように、ソフトウェアの利用者側からすると、譲渡のほうが有利な傾向にあります。著作物を自由に利用したいなら、著作権譲渡契約を締結するのがベターです。
ところで最近では、著作権譲渡契約書(あるいは制作委託契約書)をスムーズに作成できるように、必要な文言が記載されたひな形がインターネット上で頒布されています。
ただ、そうしたひな形を、何も変えずに利用するのは注意しましょう。著作権の譲渡契約で締結すべき内容は、実際にどんな著作権を譲渡するのかによって変わるからです。
たとえば、ソフトウェアの場合、すべての著作権を委託会社に譲渡するとなれば、開発会社が別の会社から開発を任された際に、その技術を応用できません。ひな形の多くはこうした部分をカバーしていないので、単に流用してしまうと後にトラブルが発生しやすくなります。
そこで、もし契約書作成が必要な場面になったら、一度弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、個々の事情を加味した上で、必要な文言・不必要な文言は何かをアドバイスすることが可能です。また作成した契約書のリーガルチェック(法的に有効なのかの確認)もできるので、トラブル発生を未然に防ぐことができます。
5、まとめ
著作権が規定している権利の内容は幅広く、すべてを理解しようとするには法律に関する深い知識が必要です。
もし契約内容の中で曖昧な部分があり、どのようにしたらいいのか判断しきれない場合は、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士にご相談ください。法的な観点から助言いたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|