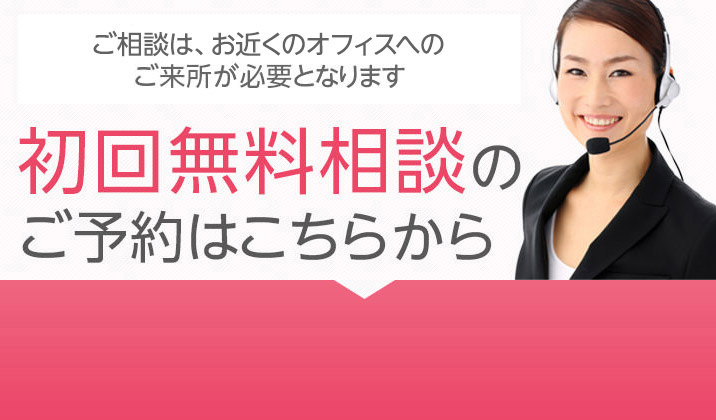熟年離婚の生活費はどうなる? 年金や財産分与についても解説
- 離婚
- 熟年離婚
- 生活費
- 岡山

厚生労働省が公表した資料によると、令和5年における岡山県の離婚件数は2750件でした。令和4年の日本全体のデータですが、同居期間20年以上で離婚した割合は23.5%であったため、岡山県でもいわゆる熟年離婚も相応に含まれていると考えられます。
離婚は夫婦間で合意さえあれば自由にできます。しかし、結婚と異なり離婚では今後の生活費を念頭に財産分与、年金の分割、子どもの養育費、慰謝料など、離婚後のお金のことについて配偶者と話し合い、合意しなければなりません。
本記事では、熟年離婚をするに際して重要な今後の生活費や年金のほか、配偶者と話し合いがまとまらない場合の対策について、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が解説します。


1、離婚後の生活費(婚姻費用)はどうなる?
婚姻費用とは、収入の多い夫(妻)に対して支払いの義務が発生するものです(民法第760条)。つまり、離婚が成立すれば婚姻費用は発生しません。
言い方を変えると、すでに離婚に向けた話し合いや手続きの段階であろうと、収入が多い夫(妻)は婚姻費用を負担する義務があります。
仮に配偶者が離婚を前提に別居して夫婦同居義務を放棄した場合でも、法的に離婚が成立していない段階では収入が多い夫(妻)は妻(夫)の生活費を婚姻費用として相応に負担する義務があるのです。
したがって、もし婚姻費用を支払わなければ、収入の少ない配偶者は家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を提起することができます。最終的には裁判で争うことになり、特別な理由がない限り、収入が多い側へ支払いするよう命令されることになるでしょう。
2、離婚後の年金分割
平成19年の厚生年金保険法改正により、離婚後に夫(妻)の厚生年金の一部を妻(夫)が受け取ることができる「年金分割」の制度ができました。
さらに、平成20年からは同年4月1日以降に権利が発生する夫(妻)の厚生年金について、婚姻期間中は国民年金保険の第3号保険者、つまり年収130万円未満であり厚生年金加入者に扶養されている妻(夫)については、相手方の同意なしに該当期間の厚生年金部分の2分の1を分割することが可能になりました。いわゆる、「3号分割」です。
3号分割は、事実婚の関係にある配偶者も可能です。
この年金分割制度を当てにして熟年離婚に急ぐ夫婦もいるようですが、年金分割については以下の点に注意が必要です。
-
(1)分割できる年金は限られている
年金分割の対象となるのは、厚生年金(標準報酬月額・標準賞与額)と旧共済年金のみです。
以下は対象となりません。- 厚生年金基金の上乗せ給付部分
- 国民年金
- 国民年金基金
- 確定給付企業年金
- 確定拠出年金
- 私的年金
つまり、自営業者や勤務先に厚生年金制度がない場合は、年金分割そのものがないのです。
また、分割対象となる厚生年金は婚姻期間中に保険料を支払った分のみであり、結婚前・離婚後に保険料を支払った部分については、分割の対象となりません。 -
(2)合意分割と3号分割は併用できる
年金分割の制度には、3号分割と合意分割の2つがあります。
合意分割とは、夫婦が共働きの場合、夫婦双方が婚姻期間中に保険料を支払った分の厚生年金については、夫婦間の話し合いなどで合意することにより最大2分の1まで分割することをいいます。
仮に婚姻期間が20年だったとして、最初の10年は会社に勤務して厚生年金保険料を払っており、後の10年は会社を辞めて第3号保険者だった場合、合意分割と3号分割のどちらになるのでしょうか。
この場合は、合意分割と3号分割を併用することになります。先ほどの例でいうと、会社に勤務し厚生年金保険料を払っていた結婚後10年間については合意分割となり、会社を辞めた後の3号分割の期間については自動的に3号分割となります。 -
(3)年金分割には時効がある
年金分割をするためには、年金事務所などで所定の手続きを経なければなりません。これは合意分割と3号分割に共通して定められています。
年金事務所などに年金分割を請求する権利は、離婚した日の翌日から起算して2年を超えると時効となり、請求すること自体ができなくなります。つまり、合意分割する場合はその割合について離婚してから2年以内に配偶者と合意した上で届出をする必要があります。
お問い合わせください。
3、離婚後の養育費
養育費とは、離婚後、子どもを監護していない親が負担する、子どもが大人として自立できるようになるまで必要なお金のことです。子どもを監護している親に対して、毎月定額を支払うケースが一般的です。
熟年離婚する夫婦の子どもは、相応の年齢に至っているものと考えられます。
では、養育費は子どもが何歳になるまで発生するのでしょうか。
法的には、養育費をいつまで支払うのかは定められていません。
ひとつの目安として、成人するまで、大学や大学院を卒業するまでといったケースが多いでしょう。
そもそも養育費は、離婚する夫婦が合意さえすれば払わなくてもよいとすることも可能です。基準はあっても法的に定められているわけではないという点は、養育費の金額についても同様です。
裁判所は子どもの年齢や人数に応じた養育費の算定表を公表していますが、これはあくまで目安に過ぎません。夫婦の話し合い次第では、子どもの進学にお金がかかるなどという理由により算定表よりも多い金額を負担することもあり得ます。
4、財産分与の対象や考え方
財産分与とは、結婚後から夫婦で形成・維持してきた財産を分配することを指します。原則、名義に関係なく夫婦の「共有財産」として、これまでの貢献度などに応じて離婚時に夫婦で分配するというものです。
熟年離婚はこれまでの貯金や退職金、住宅ローンの完済などにより財産が蓄積されていることが多いです。必然的に、若年世代と比較して財産分与の額は相応に多くなることが考えられます。
財産分与は、離婚の際に相手方に対して請求することが「できる」旨の規定であり、「しなければならない」というわけではありません。また、分割割合については「2分の1ずつ」がひとつの基準と考えるケースが一般的ですが、法律上で明確に決められているわけではありません。
したがって、財産分与の有無および財産分与の割合や分与する財産の種類については、離婚時の話し合いなどで決めることになります。
なお、結婚前から夫婦が個別に所有していた財産は「特有財産」であり、財産分与の対象とはなりません。また、婚姻期間中に相続や遺贈などにより取得した財産についても、特有財産とみなされるため、財産分与する必要はないでしょう。
5、弁護士に相談すべきケース
次のようなケースでは、できるだけ早いうちに弁護士に相談することをおすすめします。
- 配偶者が不当に高い財産分与や慰謝料を請求している
- 相手が出している条件が世間一般的に妥当なのかわからない
- 財産分与や年金分割に応じようとしない
- あなた自身が離婚原因を作ってしまった
- お互いに感情的になっている
- 調停や裁判への移行も視野に入れなければならない
- 法律や制度のことがわからない
離婚問題を解決に導いた実績が豊富な弁護士であれば、法的なアドバイスはもちろんのこと、あなたの代理人として相手方と交渉し、円満な離婚に向けた働きが期待できます。
特に配偶者が弁護士を立ててきた場合は、これ以上あなた自身で解決を試みることは難しいと判断したほうがよいでしょう。ひとりで抱え込まず、弁護士に依頼することをおすすめします。
6、まとめ
熟年離婚において念頭におかなければならないのは、離婚後の老後資金です。
離婚する以上は、今後の生活においてある程度の経済的損失が出るのは覚悟しなければならないと考えられます。しかし、配偶者からの不当な金銭の請求あるいは正当な支払いの拒否については、今後のあなた自身の生活を守るために適切な対処をとる必要があるでしょう。
離婚は、結婚と比べて大きな精神的負担が生じるものです。
離婚協議を早く終わらせたいと焦って行動した結果、配偶者と安易に妥協して今後の老後資金が不足し生活が困窮してしまった事例や、合意内容を離婚公正証書などに残しておかなかったため配偶者に合意内容を反故にされたという事例があるのです。
そのような事態に陥らないためにも、特に熟年離婚においては早めに弁護士と相談しながら進めることをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスでもアドバイスや対応を行います。お気軽に相談してください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています